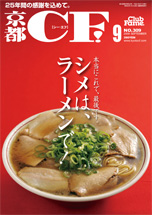クリックでスライドショー
文博(京都文化博物館/元日本銀行京都支店)のレンガ造は華やかな赤だが、レンガ造に石張りの外観を施すと白となる。
実は石張りの外観の方が、西洋ではオーソドックスであった。ローカル色の強いレンガの外観を日本の近代化の洋館としてイメージづけたのは辰野であったという。
その辰野も石張りの外観を手がけている。代表的な例として明治29年(1896年)竣工の日本銀行本店が挙げられる。一方、現存する最古のレンガの外観を見せているのが、明治39年竣工の京都文化博物館なのである。
辰野金吾は、江戸時代安政元年(1854年)に 肥後国唐津藩の下級藩士姫松家に生まれ、明治元年14歳で叔父の辰野家の養子となり、唐津では、後の首相・日銀総裁である高橋是清に英語を学んでいる。その後19歳で上京し、現在の東京大学工学部の第一回生として入学、造船を学び、転じてジョサイア・コンドルに西洋建築を学び、造家学科を主席で卒業後、英国に留学した。
3年後に帰国、翌明治17年母校工部大学校(現東京大学工学部)教授に就任することになった。
日本の近代建築設計の教育に専念し、建築学会を設立し、帝国大学工科大学学長を就任四年で退官、翌明治36年(1905年)、自らが建築家としての歩みを始めた。御年51歳の時である。
近代日本の国家建設に多大な貢献をした日本人は留学し、近代文明の本質に出会った。その驚きの瞬間の痕跡が、近代化建築遺産のあちこちに見られると思っている。辰野はそれを形に描き教えてきた。
洋館を見るたびに先人たちの、驚くべき観察眼と学習能力に脱帽し、その限りない挑戦心に感服する。その文化の底力を見習いたいものだ。
文博の東へと三条通をゆくと、柳馬場通北西角に、石張りの外観が保存された辰野の作品に出合える。銅版葺きのモスグリーンの尖がり屋根が目印だ。大正3年(1914年)に竣工した日本生命京都三条ビルである。
辰野金吾と片岡安の設計による煉瓦造2階建であるが、全面石張りされ、鉄筋コンクリートかと思ってしまう。
ところが、玄関にあたる石の階段は重厚で安定感が伝わってくるし、壁面や飾り窓の幾何学文様には気品が感じられる。入口部分には着物がディスプレイされていて、気になるショップとして要チェックである。
同じファザード保存なら中京郵便局のようにすれば更に良かっただろうと、この片側の保存に疑問を抱く。商業施設としても、オフィスビルとしてもその付加価値は高く、改築部分の有効有用性もあがっているだろう。
小生の目には、お義理で条例に合わせたような保存になっていて、改築部分がシナジー効果を狙った設計意匠なっていないのが残念でならない。そう感じるのは小生だけではあるまい。
筋向いに赤レンガタイルで覆われたアーチ窓のある建物はYMCAである。
この建物の3階には、・・・。ヴォーリズが初めて建築設計監督事務所を設けた(1908年)部屋があったところだ。勿論、その頃の建物とは同一ではないが。(現YMCA三条本館1980年竣工)
ヴォーリズは向かいの洋館をどう眺めていたのだろうかと・・・思いがよぎった。
更に東へ、富小路北西角に、石張りの外観の商業施設SACRA(旧不動貯金銀行京都三条支店)がある。こちらは関根要太郎の設計で、大正4年(1915年) 竣工の、銅版葺煉瓦造3階建である。積み木を積んだようでいて、壁面の凹凸を強調した意匠は、重厚感が溢れている。
同じ石張りであっても、日本生命の華麗で気品を帯びたイメージとは違い、力強い線が強調され、型枠ではめられた様な抽象的なオーダーや、銅版の屋根に設けられた大きな紋章などは、大胆で宇宙的なイメージさえ抱く。
現在、多数のテナントが営業して20年近くなるだろうが、一棟借りで一ブランドのショップであれば、更に人気が出そうな感さえした。
レトロな建築遺産が商業施設として利用されだしたのはSACRAが魁であったように思う。
さて、次に進もう。富小路通を渡り東へ入る。
三条通で一番話ネタの尽きない建物であろう。ここはレンガ造洋館仕立のダマシンカンバニー(旧・家邊徳時計店)である。
この外観全体から見ても、西側の外壁に見られる新旧のレンガ積み址から見ても、レンガ造であることを疑う者はいないであろう。隅石やバルコニーなどの飾りレリーフ、オーナメントやアーチ窓、どれを見てもレンガ造の洋館であることを否定できないはずである。
ところが、データを見ると、竣工: 1890(明治23)年、 設計: 不明、 構造: 木造2階建、 文化財指定: 登録有形文化財、とある。
つまり、木造2階建レンガ張洋館仕立なのである。
テント上部のアーチは特異である。近代建築遺産を見てきたが、楕円型アーチを見るのはここだけである。更に、アーチの下のどこにも飾りのオーダー(柱)がない。
加えて、テント下部のショーウィンドーの頭上に当たる部分には、木製のレリーフがはめられている。
この建築時期には、木造洋館を多く残したヴォーリズは10歳で、来日もしていない。
京都には、器用な職人さんがいたものだと感心する。 様式にとらわれず様式を採用する自由で無国籍な発想が見られる。
このダマシンカンバニーの存在感は、他に変えがたい貴重なものである。「下町の貴賓室」と名づけよう。
御幸町東南角まで進むとアートコンプレックス1928(元毎日新聞社京都支局)がある。
辰野の指導を受けた武田五一の設計による鉄筋コンクリート造地上3階、地下1階で、昭和3年(1928年)竣工のビルである。
ワーゲンバスが玄関先に置かれ、星型バルコニーと星型窓に戸惑いを覚える不可思議な建物である。
建築家若林広幸氏が譲り受け、ピンクのカラーリングを施し、情報発信商業施設として管理運営されている。
明治から昭和にかけての古き良き時代の建築物が、三条通に生きたまま、まるで京都の有り様を証言しているようだ。
時代を駆け抜けても光り続け、更に生き続けるものを創り出せと、聞こえてくる。
実は石張りの外観の方が、西洋ではオーソドックスであった。ローカル色の強いレンガの外観を日本の近代化の洋館としてイメージづけたのは辰野であったという。
その辰野も石張りの外観を手がけている。代表的な例として明治29年(1896年)竣工の日本銀行本店が挙げられる。一方、現存する最古のレンガの外観を見せているのが、明治39年竣工の京都文化博物館なのである。
辰野金吾は、江戸時代安政元年(1854年)に 肥後国唐津藩の下級藩士姫松家に生まれ、明治元年14歳で叔父の辰野家の養子となり、唐津では、後の首相・日銀総裁である高橋是清に英語を学んでいる。その後19歳で上京し、現在の東京大学工学部の第一回生として入学、造船を学び、転じてジョサイア・コンドルに西洋建築を学び、造家学科を主席で卒業後、英国に留学した。
3年後に帰国、翌明治17年母校工部大学校(現東京大学工学部)教授に就任することになった。
日本の近代建築設計の教育に専念し、建築学会を設立し、帝国大学工科大学学長を就任四年で退官、翌明治36年(1905年)、自らが建築家としての歩みを始めた。御年51歳の時である。
近代日本の国家建設に多大な貢献をした日本人は留学し、近代文明の本質に出会った。その驚きの瞬間の痕跡が、近代化建築遺産のあちこちに見られると思っている。辰野はそれを形に描き教えてきた。
洋館を見るたびに先人たちの、驚くべき観察眼と学習能力に脱帽し、その限りない挑戦心に感服する。その文化の底力を見習いたいものだ。
文博の東へと三条通をゆくと、柳馬場通北西角に、石張りの外観が保存された辰野の作品に出合える。銅版葺きのモスグリーンの尖がり屋根が目印だ。大正3年(1914年)に竣工した日本生命京都三条ビルである。
辰野金吾と片岡安の設計による煉瓦造2階建であるが、全面石張りされ、鉄筋コンクリートかと思ってしまう。
ところが、玄関にあたる石の階段は重厚で安定感が伝わってくるし、壁面や飾り窓の幾何学文様には気品が感じられる。入口部分には着物がディスプレイされていて、気になるショップとして要チェックである。
同じファザード保存なら中京郵便局のようにすれば更に良かっただろうと、この片側の保存に疑問を抱く。商業施設としても、オフィスビルとしてもその付加価値は高く、改築部分の有効有用性もあがっているだろう。
小生の目には、お義理で条例に合わせたような保存になっていて、改築部分がシナジー効果を狙った設計意匠なっていないのが残念でならない。そう感じるのは小生だけではあるまい。
筋向いに赤レンガタイルで覆われたアーチ窓のある建物はYMCAである。
この建物の3階には、・・・。ヴォーリズが初めて建築設計監督事務所を設けた(1908年)部屋があったところだ。勿論、その頃の建物とは同一ではないが。(現YMCA三条本館1980年竣工)
ヴォーリズは向かいの洋館をどう眺めていたのだろうかと・・・思いがよぎった。
更に東へ、富小路北西角に、石張りの外観の商業施設SACRA(旧不動貯金銀行京都三条支店)がある。こちらは関根要太郎の設計で、大正4年(1915年) 竣工の、銅版葺煉瓦造3階建である。積み木を積んだようでいて、壁面の凹凸を強調した意匠は、重厚感が溢れている。
同じ石張りであっても、日本生命の華麗で気品を帯びたイメージとは違い、力強い線が強調され、型枠ではめられた様な抽象的なオーダーや、銅版の屋根に設けられた大きな紋章などは、大胆で宇宙的なイメージさえ抱く。
現在、多数のテナントが営業して20年近くなるだろうが、一棟借りで一ブランドのショップであれば、更に人気が出そうな感さえした。
レトロな建築遺産が商業施設として利用されだしたのはSACRAが魁であったように思う。
さて、次に進もう。富小路通を渡り東へ入る。
三条通で一番話ネタの尽きない建物であろう。ここはレンガ造洋館仕立のダマシンカンバニー(旧・家邊徳時計店)である。
この外観全体から見ても、西側の外壁に見られる新旧のレンガ積み址から見ても、レンガ造であることを疑う者はいないであろう。隅石やバルコニーなどの飾りレリーフ、オーナメントやアーチ窓、どれを見てもレンガ造の洋館であることを否定できないはずである。
ところが、データを見ると、竣工: 1890(明治23)年、 設計: 不明、 構造: 木造2階建、 文化財指定: 登録有形文化財、とある。
つまり、木造2階建レンガ張洋館仕立なのである。
テント上部のアーチは特異である。近代建築遺産を見てきたが、楕円型アーチを見るのはここだけである。更に、アーチの下のどこにも飾りのオーダー(柱)がない。
加えて、テント下部のショーウィンドーの頭上に当たる部分には、木製のレリーフがはめられている。
この建築時期には、木造洋館を多く残したヴォーリズは10歳で、来日もしていない。
京都には、器用な職人さんがいたものだと感心する。 様式にとらわれず様式を採用する自由で無国籍な発想が見られる。
このダマシンカンバニーの存在感は、他に変えがたい貴重なものである。「下町の貴賓室」と名づけよう。
御幸町東南角まで進むとアートコンプレックス1928(元毎日新聞社京都支局)がある。
辰野の指導を受けた武田五一の設計による鉄筋コンクリート造地上3階、地下1階で、昭和3年(1928年)竣工のビルである。
ワーゲンバスが玄関先に置かれ、星型バルコニーと星型窓に戸惑いを覚える不可思議な建物である。
建築家若林広幸氏が譲り受け、ピンクのカラーリングを施し、情報発信商業施設として管理運営されている。
明治から昭和にかけての古き良き時代の建築物が、三条通に生きたまま、まるで京都の有り様を証言しているようだ。
時代を駆け抜けても光り続け、更に生き続けるものを創り出せと、聞こえてくる。
5256-140911-秋
京都文化博物館
中京郵便局
日本生命京都三条ビル
YMCA
SACRA
旧不動貯金銀行
ダマシンカンバニー
家邊徳時計店
アートコンプレックス1928
毎日新聞社京都支局
三条通
柳馬場通
富小路通
御幸町
中京郵便局
日本生命京都三条ビル
YMCA
SACRA
旧不動貯金銀行
ダマシンカンバニー
家邊徳時計店
アートコンプレックス1928
毎日新聞社京都支局
三条通
柳馬場通
富小路通
御幸町
辰野金吾
ヴォーリズ
武田五一
若林広幸
片岡安
東京大学
ヴォーリズ
武田五一
若林広幸
片岡安
東京大学
写真/画像検索
関連コラム
京都近代建築遺産といえば……
- ヴォーリズの京都に残した洋館
足跡を追へば何が垣間見える - 洋館を訪ねて4 三条四条間
「ポスト千年の都」近代の象徴を受け継ぎ、平成京都人の心意気を。 - 洋館を訪ねて2 三条通
レンガ色の街を歩けば、京都人気質の音がする - 洋館を訪ねて 烏丸三条
ビルヂングは京町家に匹敵する近代の宝
レンガといえば……
- 洋館を訪ねて4 三条四条間
「ポスト千年の都」近代の象徴を受け継ぎ、平成京都人の心意気を。 - 洋館を訪ねて2 三条通
レンガ色の街を歩けば、京都人気質の音がする - 洋館を訪ねて 烏丸三条
ビルヂングは京町家に匹敵する近代の宝